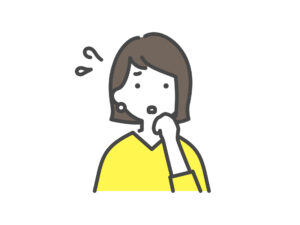
脳出血後に話をするだけで息苦しくなるんです・・・

脳梗塞後に特に疲れやすくなったように感じます・・・
脳卒中後に疲れを感じやすくなった方は多いと思います。
脳卒中後の疲労についての研究では有病率は正確には不明なままですが、高い割合で長期間持続的に『脳卒中後の疲労(Post-Stroke Fatigue)」を保有し続ける実態があることが言われています。
今回の記事では脳卒中後の疲労(Post-Stroke Fatigue)について解説していきます。
疲労とは
疲労とは、過度の肉体的および精神的活動、または疾病によって生じた独特の不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減退状態である
日本疲労学会(2011)
疲労は『疲労』と『疲労感』に分けられる。
疲労:心身への過負荷により生じた活動能力の低下
疲労感:疲労が存在することを自覚する感覚
疲労によって起こる身体の活動能力の減退
疲労によって起こる身体症状として以下のものが考えられる。
- 思考能力の低下
- 刺激に対する反応の低下
- 注意力の低下
- 注意散漫
- 動作緩慢
- 行動量の低下
- 眼のかすみ
- 頭痛
- 肩こり
- 腰痛
脳卒中後の疲労
脳卒中後の疲労は、「肉体的または精神的活動中に発生し、通常は休息によって改善されない、倦怠感、エネルギー不足、および努力への嫌悪感を伴う初期の疲労感」として説明されています。
Post-Stroke Fatigue: Epidemiology, Clinical Characteristics and Treatment
原因は「脳卒中」の発症に加え、「パーソナリティ特性」「身体的要因」「心理的要因」「行動要因」「社会的要因」「環境要因」が複数関連すると言われています。
そして、脳卒中後の疲労で日常生活動作の低下(ADL低下)、生活の質の低下(QOL低下)などが生じ、適切に管理できないと「鬱(うつ)」の発症を招くことも言われています。
一般的な疲労と脳卒中後の疲労は区別される
脳卒中後の疲労は一般に脳卒中前に経験した疲労とは質的に異なると言われています。
疲労は入院後すぐに体験され、退院後早期、または発症前のライフスタイルを再開させる際に体験されやすいことが明らかになっています。
脳卒中後は認知的なタスク(マルチタスクなど)で身体的な疲労もですが、精神的な疲労によって興味の欠如やモチベーションの低下につながることもあります。
疲労に対するさまざまな治療
脳卒中後の疲労は色々な要素が関連しています。
疲労を軽減するために薬理、物理(リハビリ)、心理的治療など身体的側面と認知的側面の両方を対象とするアプローチが必要とされています。
薬理的治療と疲労
抗うつ薬またはカウンセリングは疲労の精神的側面に対処する可能性があります。
※鬱(うつ)病と疲労は一般的に切り離されている。
理学療法と疲労
運動が身体機能を改善させ、疲労を軽減すると考えられています。
段階的な身体活動プログラムが脳卒中後の疲労のアプローチとして推奨されています。
また、段階的活動トレーニングプログラムと認知療法を組み合わせることで、脳卒中後の持続的な疲労を大幅に軽減させることも示されています。
心理療法と疲労
認知行動療法が脳卒中後の疲労に有効である可能性がある。
自身の行動客観的に分析し、ストレスがかかっている行動を押さえたり、ストレスがかからない自身にとって良い活動を生活パターンに組み込んだりして、行動の変化を促進することが重要であると考えられています。
環境と疲労
病院外での推奨事項には、「運動」「栄養」「休息」「リラクゼーション」が含まれると言われています。
ストレスがかかっている環境に身を置き続けると、よりネガティブな思考になり疲労につながるため上記の推奨事項を環境面から変えていくことも重要ですね。
まとめ
脳卒中後の疲労は解明されていないことが多い症状です。
脳卒中後の疲労は休息では改善されないと言われているから、「疲れたから休みましょう」は本当に正しいのか?は一度振り返ってみないといけませんね。
「なぜ疲労になるのか?」
原因を探って計画的に対処する力をつけることが大切です。
特に退院後の方は毎日誰か専門のスタッフが近くにいるわけではないので、自ら変化する力をつけないといけません。
「自分自身で変化できるようになりたい」
と思っている方はぜひお問い合わせください。
公式LINEに登録するとリハビリに関する限定情報を受け取ることができます。
また、個別相談もしているので脳カラ公式LINEをご登録ください。
参考文献
- The prevalence of fatigue after stroke: A systematic review and meta-analysis
- Post-Stroke Fatigue: Epidemiology, Clinical Characteristics and Treatment
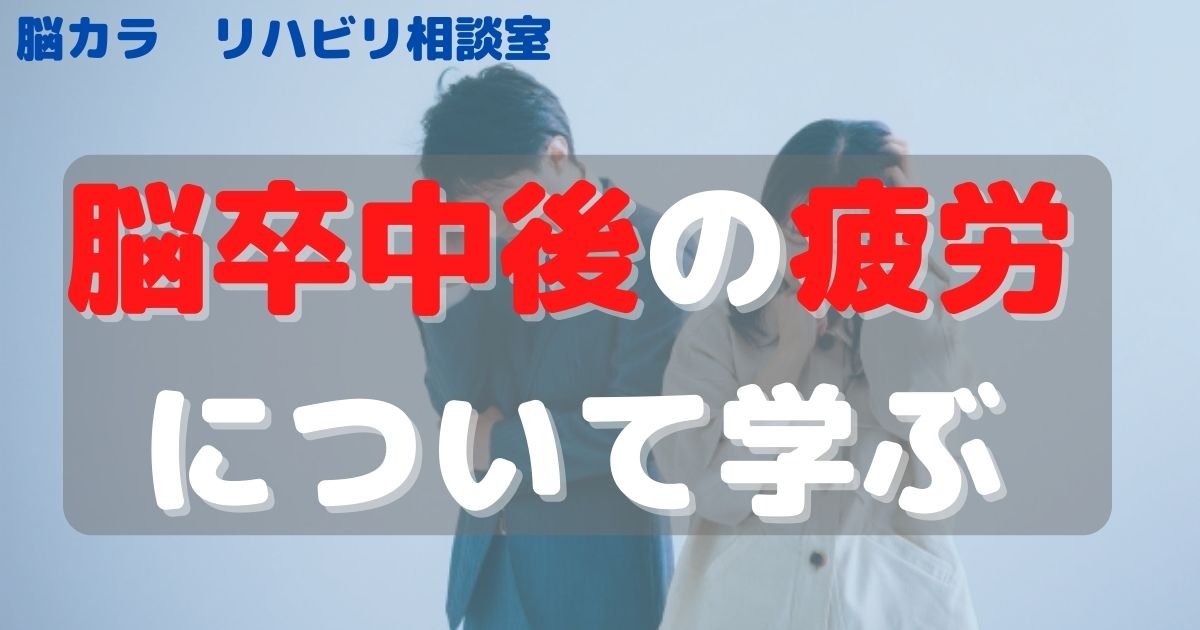


コメント