脳卒中後の歩行を阻害する因子として、麻痺足の足趾がギューっと曲がってしまう症状があります。
これはクロートゥ(Craw toe)と呼ばれることもあります。
この記事では、現在、クロートゥ(Craw toe)でお悩みの方へ、クロートゥ(Craw toe)について原因とリハビリについてまとめた内容になります。
クロートゥ(Craw toe)が歩行に与える影響
クロートゥは麻痺側の足趾がギューっと曲がってくる症状です。
足趾が曲がった状態で立ったり歩いたりすると指先が過剰に地面にあたり痛み刺激になります。そしてそのまま歩き続けると痛みが強くなったり傷ができ歩行に影響が出る可能性もあります。

クロートゥ(Craw toe)はなぜ起こるのか?
クロートゥ(Craw toe)は、緊張性足趾屈曲反射(Ronic toe flextion reflex:TTFR)とも呼ばれており、脳が障害されることで起こる錐体路障害(痙性と同様の症状)で起こると言われています。
つまり、『脳』からの運動指令が『筋肉』にうまく伝わらなくなることで起こる症状です。
日常生活動作の場面では、立位や歩行といった足への刺激や筋緊張が高まりやすい動作で顕著に起こることが特徴です。これは難しい動作ほど脳からの運動司令が複雑になるため処理が追いつけなくなることが要因となります。
クロートゥ(Craw toe)による二次障害
クロートゥ(Craw toe)は立位バランスや歩行をする際の阻害因子となりますが、二次障害も考えないといけません。
- 足趾の変形
- 足趾の炎症や傷
- 筋力低下
- 転倒
足趾の変形
足趾のDIP関節(遠位趾節間間接)とPIP関節(近位趾節間関節)の屈曲位、MTP関節の伸展位になる状態です。
足趾の上記のように筋緊張が亢進することが長期間続くことで、足趾がクロートゥ(Craw toe)のように変形してしまうこともあります。
足趾の炎症や傷
クロートゥ(Craw toe)の状態で立位や歩行を継続して行うことで、足趾先端部に床面が接触し、局所的な接触刺激が強くなり炎症や傷ができる可能性もあります。
筋力低下
変形や痛みによって、麻痺足への荷重が少なくなったり歩行することを躊躇われたりし、麻痺足へ負荷量や全体的な運動量が少なくなり筋力低下が起こることがあります。
転倒
クロートゥにより、変形、炎症や傷の痛み、筋力低下などが総合的に影響して、立位バランス低下や歩行能力低下となり転倒の危険性が増します。
転倒により、骨折になると長期療養を要しさらに二次障害を助長することになります。
クロートゥ(Craw toe)に対しての介入方法
クロートゥ(Craw toe)への介入方法は、装具療法、ボツリヌス療法(ボトックス)、電気療法、リハビリテーションがあります。
- 装具療法
- ボツリヌス療法(ボトックス)
- 電気療法
- リハビリテーション(次の項目で解説)
1.装具療法
クロートゥ(Craw toe)による緊張の高まりを装具を使用することでサポートすることができます。
装具の種類は主に、短下肢装具(ankle-foot-orthoses:AFO)やinhibitor bar(インヒビター バー)、toe spread(トゥスプレッド)などのサポーターがあります。
装具については、足底アーチが緊張によって高くなっている状態を抑えるために指先までサポートしているものが必要です。
サポーターについては、クロートゥ(Craw toe)によって曲がっている足趾の間にクッションをおき、足底の接地面を増やすことで緊張が抑えられたり、痛みが軽減する効果があります。
2.ボツリヌス療法(ボトックス)
ボツリヌス療法は、痙縮に対してに治療方法としても有効で、脳卒中治療ガイドライン2015においても推奨グレードAとされています。
クロートゥ(Craw toe)の対処方法についても、ボツリヌス療法により痙縮による下肢の筋緊張を抑え、リハビリテーションを適切に行うことは有効となる可能性があります。

3.電気療法
電気療法とは、神経や筋に対して刺激を与え筋活動を与える方法です。
クロートゥ(Craw toe)は、足趾の屈筋の緊張が亢進している状態です。しかし、原因は足趾の屈筋ではなく、痙縮によって下腿三頭筋や足底筋などの緊張が高まっていることによって足趾の屈筋の緊張が亢進している状態になっています。
電気刺激によって、下肢の目的とする筋肉に刺激を与えること、そしてリハビリを併用することでクロートゥの影響が少なくなる可能性もあります。

クロートゥ(Craw toe)へ ひとりでできるリハビリについて
クロートゥ(Craw toe)への対処方法として、リハビリテーションとの併用がとても重要になります。
そして、クロートゥ(Craw toe)の原因となっている足趾の緊張亢進については、脳が正しい情報を得られていないことで、脳から筋肉への運動指令が正しく送れないため結果的にクロートゥ(Craw toe)が起きていると考えています。
- 立ち上がり直後からクロートゥ(Craw toe)になる方
- 歩き出すとクロートゥ(Craw toe)になる方
リハビリテーション実際をご説明していきます。
- 『感覚』を意識すること
- 動作は『ゆっくり』行うこと
1.立ち上がり直後からクロートゥ(Craw toe)になる方
立ち上がり直後のクロートゥ(Craw toe)は立ち上がりが影響しています。
以下に立ち上がり動作の手順とポイントをお伝えします。
- 座位の確認(左右のお尻の感覚)
- お辞儀の確認(お尻から太ももへの体重移動と足裏の体重の乗り方)
- 伸び上がりの確認(左右の足裏に体重が乗ったまま立位になれるか)
1.座位の確認(左右のお尻の感覚)
座位から左右のお尻に感覚を感じているかを確認します。
クロートゥになりやすい方は、座り方からいい方に偏っていることが多いです。


2.お辞儀の確認(お尻から太ももへの体重移動と足裏の体重の乗り方)
座位が確認できたら、次はお辞儀までを確認します。
お辞儀する時にいい方に偏っていないか、左右均等に体重移動ができているかを確認しましょう。


3.伸び上がりの確認(左右の足裏に体重が乗ったまま立位になれるか)
お辞儀が確認できたら、実際に立ち上がりになります。
立ち上がりでは、左右の足裏への体重がしっかりのっているか、特に踵を意識しながら実践します。


2.歩き出すとクロートゥ(Craw toe)になる方
歩き出すとクロートゥ(Craw toe)になる方は、麻痺足の支え方が影響している可能性があります。
ここでは、特に一歩目を出す時に麻痺足の支えて、いい方の足を出す場面での支え方とポイントを説明します。
- 麻痺足への体重移動の確認 Part1
- 麻痺足への体重移動の確認 Part2
- いい方の足を振り出す
1.麻痺足への体重移動の確認 Part1
いい方の足から一歩目を出すときは、麻痺側の足へ体重移動をしなければいけません。
クロートゥ(Craw toe)になる方の歩き初めの特徴は、麻痺足への体重移動が十分に行えていないことが影響しています。
そして、足裏を細分化して体重移動していくことが重要です。

2.麻痺足への体重移動の確認 Part2
Part1で内側を感じられたら、麻痺足の体重移動の確認Part2へ以降です。
さらに足裏を細分化して体重を移していきます。

3.いい方の足を振り出す
1,2で麻痺足に体重移動ができたら、いい方の足が軽くなっていると思います。
軽さを確認できたらいい方の足をゆっくり前に振り出しましょう。
この体重移動のポイントは麻痺による緊張の高まり(痙縮)を抑えながら、いかに麻痺足で支えられるかが重要になります。
そして脳カラのリハビリでは、特に感覚を重要視しており、感覚を感じやすい状態に持っていくためにはゆっくり丁寧に動くことが大切です。
ぜひ、ご自身がどのタイミングでクロートゥ(Craw toe)が出るのかを確認した上で実践してみてください。
まとめ
いかがでしたか。
クロートゥ(Craw toe)は脳卒中当事者の方の歩行に影響はとても大きいです。
しかし、適切なリハビリや動き方をご自身で身につけることで変化を実感できるかたも多くおられます。
今まで「麻痺だから・・・」「もうよくならない・・・」と諦めている方も、今回の記事を見て少しでも変化を感じられた方は諦めるのはまだ早いと思います。
ひとりで悩んでいる時間は勿体ありません。どんなことでもいいので、お気軽にお問い合わせください。
脳カラ公式LINEへの登録お願いいたします。
公式LINEに登録するとリハビリに関する限定情報を受け取ることができます。
また、個別相談もしているので、是非ご登録ください。
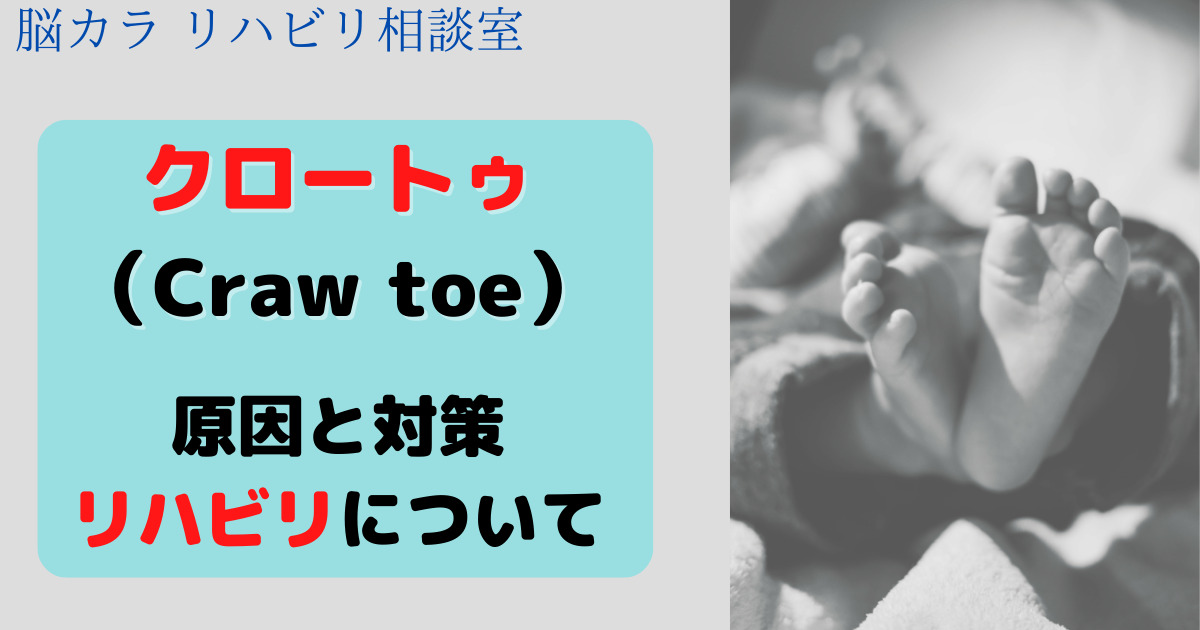





コメント