脳カラでは脳卒中当事者・家族が自律的に決める目標設定を重要にしています。
極端に言うと、目標設定さえ具体的に細かく決めれたら、リハビリ内容がなんであろうと結果が出る(と言っても過言ではないと)と考えています。
今回は、多くの方が聞いたことのある目標設定の代表例『SMARTの法則』と具体的に私がクライアントと立てている目標設定の例をご紹介します。
SMARTの法則とは
SMARTの法則とは、目標の作り方のことを言います。
Specific:具体的、わかりやすいの意味
Measurable:計測可能、数字になっているを意味
Achievable:同意して、達成可能なを意味
Relevant:関連性を意味
Time-bound:期限が明確、今日やるを意味
頭文字をとった言葉で、目標を達成するための5因子と言われています。
介護保険や自費リハビリにて退院後の生活期リハビリをしている方、このSMARTの法則を知っておくと目標設定や達成に活用できます。
あくまで目標を立てるのはあなた自身でリハビリスタッフやケアマネージャーが決めるものではありません。このことは忘れないようにしてください。
Specific(具体性)
目標は具体的なほど良いです。
抽象的では、目標を達成する具体的な行動も抽象的になっていまったり、「あれもしないと」「これもしないと」と迷ってしまいます。
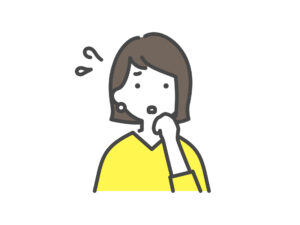
う〜ん。
目標はもっと歩きが良くなることです。
また、麻痺手はいい方のように動かせることです。

目標は、家族と温泉旅行に一緒に行くために長距離を歩けることです。
あと、階段も安定して登れないといけないので練習しています。
安定して歩けることで家族も自分も楽しめるからね。
目標が具体的であればあるほど、目標を達成するために必要なアクション(リハビリ内容)が細かく設定できますね。
Measurable(数値化する)
効率的で有効性の高い目標管理を実施するためには、目標は数値化しないといけません。
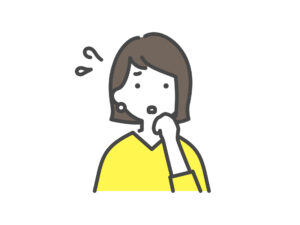
う〜ん。
目標はもっと歩きが良くなることです。
また、麻痺手はいい方のように動かせることです。
例えば上のような抽象的な目標を立てたとしましょう。
どうやって良くなったかを判定しますか?抽象的だと良くなっているかどうかが自分判断になりますよね。
よくあるのは「私は良くなっている実感ないけど、療法士の方は良くなっていると言っています。」というやりとりです。
では、数値化するとどうでしょう。

・目標は旅行に行くために最低でも1kmは連続で歩きたい。
・麻痺手を使って食事をする時間を20分以内にできるようになりたい。
このように目標を少しでも数値に落とし込むことで、「現状どのくらい連続で歩けるか?」「麻痺手をどのくらい使って、どのくらい時間がかかって食事をしているのか?」が評価数値となり、目標に対して現状がどのくらいかを把握できます。
ここは評価のプロである理学療法士や作業療法士と一緒に決めることが大切ですね。
Achievable(達成可能性)
目標は達成可能なものにすること大切です。
より高い成果を求めて、非現実な目標を設定してしまうとうまくいかないので注意が必要です。
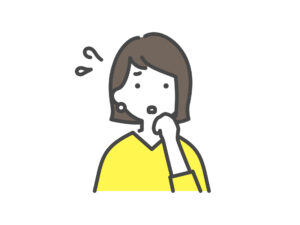
1ヶ月後に前みたいに綺麗に歩けるようになりたい
3ヶ月後に麻痺手を完全に治したい
希望としては良くしたいという気持ちでわかりますが、「現実的に達成できるのか?」はまた別の話です。
また、抽象的だと何を持って達成したことになるのかが不明確なので、頑張ってリハビリをしていても次第にモチベーションが低下し効率も悪くなり、目標設定自体の意味を失ってしまいます。

目標は3ヶ月後、旅行に行くために最低でも1kmは連続で歩きたい。
そのために必要な細かい目標は・・・
①1ヶ月後までに杖を使って500m連続で歩く
②2ヶ月後までに杖を使って1km歩く
③3ヶ月後までに毎日1kmは連続で歩く
大きな目標を立てるのは重要ですが、その目標を達成するための細かい目標を段階的に立てれることがポイントになります。
Relevant(関連性)
「目標を達成した先に何があるのか?」「何のために目標を達成するのか?」この関係性が自分の中で明確になることで、モチベーションの向上・維持ができます。

私が家族と旅行に行きたかったのは安心した姿を見せたいからです。
旅行に一緒に行けてとても喜んでもらえて嬉しかった。
次は〇〇をして家族をもっと安心させたり喜ばせたりしたい。
トビ子ちゃんのように旅行に行きたい理由が「家族を喜ばせたいから」「安心させたいから」と、なんのための目標なのかが明確になっていたらいいですね。
目標を達成したらそこでおしまいではなく、次々とやりたいことや目標が定まってきますね。
Time-bound(期限)
目標は必ず期限を決めましょう。
いくら目標を具体的で数値化できていても、期限を決めていないとモチベーションを高く保つことができません。
期限があるからそこに向かって集中して取り組めます。逆に期限がないと、そのうち「あれもしたい」「これも目標」などせっかく立てた目標が別の目標にすり替わったり、忘れたりしますね。
目標設定の具体例:ADOC
私はクライアントさんとの間でADOCという目標ツールを使用して目標設定しています。
ADOCは、イラストなどを見ながら自分が本当にしたい・やりたいことを共有する目標設定シートになります。
細かく設定ができるのと当事者と医療従事者で目標を共有できるので、間違った方向に進むことはないし、当事者の方が選択して決めるので本当にやりたいことが見つかる可能性があります。
以下、私のクライアントさんと共有したADOC内容をご紹介します。


このようにできるだけ具体的な目標で期限を決めて目標に向かってリハビリを行なっております。
月1回は必ず経過を見るようにし、どんどん更新しています。
このように目標が見えることと変化がわかることでモチベーションも上がり、目標達成率がグーンと上がっていきます。(実感も含めそう感じています)
まとめ
いかがでしたか。
目標をなんとなく立てていたり、療法士から目標を聞かれた時も「事務手続き上必要なことでしょ」と思っていた方は間違いですよ。
リハビリ内容より目標の方が大切です。目標があるからリハビリ内容が決まります。
そして、自分自身で目標を決めるといった過程が重要です。
もし「目標の立て方がわからない・・・」「一緒に決めてほしい」と言う方は以下の公式LINEからメッセージをください。
少しでも多くの方に自分が本当にしたい・やりたいことを目標にしてほしいと思っています。
是非、お気軽にご相談くださいね。
脳カラ公式LINEへの登録お願いいたします。
公式LINEに登録するとリハビリに関する限定情報を受け取ることができます。
また、個別相談もしているので、是非ご登録ください。



コメント