
人間の歩行はとても効率的な動きとなっています。
しかし、脳卒中後の麻痺による異常歩行ではこの効率的な動きが破綻してしまいます。
この脳卒中後の歩行を改善するためには効率的な歩き方を身につける必要があり、身につけるには正常歩行がどうなっているかを学び、理解することが第一歩です。
この記事では、運動学をもとに人間が歩きを分類し、特に重要な支持期における重心の移動や床反力、作用する筋の働きなどを解説します。
歩行の分類
歩行には足で体重を支える立脚期と、足を前に振り出す遊脚期の大きく分けて2期あります。
また立脚期と遊脚期は細かく分けることができます。
- 初期接地期 initial contact(IC)⇨足が床に接地した瞬間
- 荷重応答期 loading response(LR)⇨足の裏全体が地面に接地
- 立脚中期 med stance(MSt)→踵が床から離れる
- 立脚終期 Terminal stance(TSt)→つま先が床から離れる
- 前遊脚期 pre swing(PSw) ⇨つま先が床から離れた瞬間

- 遊脚初期 initial swing(ISw)⇨足が床を離れ反対の足を越すまで
- 遊脚中期 med swing(MSw)⇨反対の足を越す
- 遊脚終期 Terminal swing(TSw) ⇨足が床に着く前

正常歩行の重心の動き
【重心の高さ】
単脚支持期(歩行中に片足で支える場面)で重心の高さは高くなり、両脚支持期(歩行中に両方の足で支える場面)で重心の高さは低くなります。
そして、重心の高低が交互に波のように起こります。
【進行方向速度の変化】
重心が最も高い時に速度が遅くなり、重心が最も低い時に速度が速くなります。
つまり、単脚支持期(歩行中に片足で支える場面)で速度は遅くなり、両脚支持期(歩行中に両方の足で支える場面)で速度は速くなることがわかります。
【重力を利用した重心の上下移動】
重心の高さの変化と速度の変化については、重心が高くなる過程では速度が遅くなり、重心が低くなる過程では速くなります。(振り子で表現)
これは重力を利用して効率的な歩行になっていることを示しています。

歩行に影響する床反力
床反力とは、「床にかかる力と床から足にかかる反力」のことを言います。
床反力については、足から床、床から足にかかるベクトルと力は同じ力が入っている
踵接地はブレーキ作用、全面接地からつま先接地ではアクセル作用に床反力は働きます。

歩行の際は一方の足はアクセル作用、他方の足はブレーキ作用と交互にバランスを取り合いながら歩行の安定性や速度を調整しています。
歩行と足の裏の軌跡
歩く際に重要になってくる体の部位は足の裏です。
なぜかというと、床と唯一接地している体の部位だからです。
そして、歩行の際に床と一番最初に接地する足の裏の部位は踵(かかと)ですね。
何をするにも始まりが大切と言いますが、まさに歩行においても始まりの踵(かかと)はとても重要になるんです。

踵接地の重要性
足裏の着き方と筋活動の関係を説明します。
歩行時の踵接地の際には踵からブレーキ作用の床反力が生じます。
そして、足関節より後ろに床反力が生じている際は下腿では前面の筋(前脛骨筋)が働きブレーキ作用に貢献しています。
では、踵接地から足裏全体接地、つま先接地に移行するとどうなるかというと、前方向にアクセル作用の床反力が生じます。
そして、足関節より前方に床半力が生じている際は下腿では後面の筋(下腿三頭筋)が働き、アクセル作用に貢献してきます。

しかし、片麻痺になると踵接地ができなくなることでブレーキ作用が生まれず、常に下腿三頭筋が働いたり、無理やりブレーキをかけようと膝がピーんと伸びてしまう代償動作が出現します。
結果的に反張膝やロッキングといった症状が出現してしまうのです。

まとめ
いかがだったでしょうか。
この記事では、楽な歩きを身につけるための第一歩として、まずは正常歩行の運動学の観点からポイントを絞ってまとめてみました。
最後に脳卒中後の麻痺による異常歩行の床反力と筋緊張の関係でお伝えしましたが、麻痺だから緊張が高くなるのではなく、歩き方がうまく意識できていないから緊張が高まる状態になります。
そして、より効率的な歩行に近づくために、リハビリで動き方を学んだり、リハビリ補助として装具を使用したりします。リハビリをしたから、装具をつけたから良くなるのではなく、自分に合ったリハビリ方法や補助装具を使用して、自ら意識しながら行うことが大切になります。
今回の記事がそのための参考書になれば嬉しいです。
脳カラ公式LINEへの登録お願いいたします。
公式LINEに登録するとリハビリに関する限定情報を受け取ることができます。
また、個別相談もしているので、是非ご登録ください。
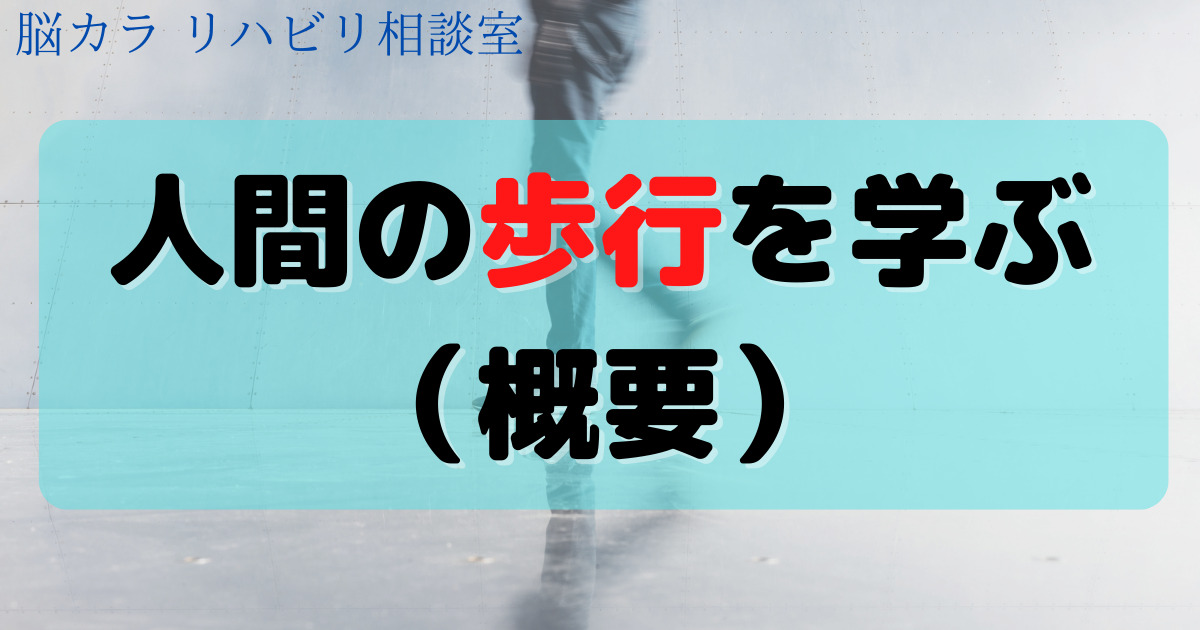


コメント