リハビリにおいて“目標設定”はとても重要なことです。
目標が具体的であればあるほど、変化が分かり効果を実感できます。
しかし、実際の現場では「目標を立てたままで終わっている」状態になっている場合も多くあります。
目標を立てっぱなしになっている原因は、『目標』と『目的』が同じになっているためです。
これは当事者の方だけでなく、医療従事者にも同じだと思っている方がいるので、是非最後までご覧いただきたいです。
『目的』と『目標』の違いとは?
- 目的:ありたい姿、最終的に到達したい場所や部分
- 目標:目的を達成するためにクリアすべきステップ(マイルストーン)
同じように目指す場所や部分、指標ではあるが全体から見たら『目的』=ゴール、『目標』=目的までの指標といった意味合いがあります。

車を運転する人ならイメージがつきやすいかもしれませんが、旅行に行くときなど「目的地」を設定しますが、この目的地=目的(ゴール)ですね。
そしてカーナビの機能には立寄地という設定もでき、その「立寄地」=目標(目的の指標)になるとイメージしやすいですね。
目的と目標の比較
| 目的 | 目標 | |
| 対象範囲 | 広い | 狭い |
| 行動 | 全体的 | 具体的 |
| 測定 | 測定が難しい | 簡単に測定ができる (一目でわかる) |
| 時間軸 | 長期間 | 短期間または中期間 |
| 要素 | 理想、ありたい姿 | 現実的 |
| 例 | 「体が良くなる」 「幸せに過ごす」 | 「入浴が簡単にできる」 「一人で買い物に行ける」 「装具なしで歩行ができる」 |
『目的』はありたい姿、理想とする最終的に到達したい場所や部分
実現しようとして目指す事柄、行動の狙い、目当て(デジタル大辞泉より)
『目的』と目標との違い
- 目標よりも抽象的で長期的にわたる
- 具体的な数値よりも意志や方向性に重点がある
- 数値で表せない事柄やものが多い
『目標』は目的を達成するためにクリアすべきステップ
そこに行き着くように、またそこから離れないように目印にするもの。
行進するにあたって実現、達成を目指す水準。(デジタル大辞泉)
目標は目的に向かってブレずに前進するために定める具体的な水準のことです。
目標と目的との違い
- 目的よりも具体的
- 目指す地点、数値、数量に重点がある
- 定量化(数値)に表されることが多い
目的と目標の違いが理解できないことで起こる失敗
先ほど説明したように、『目的』はゴール地点(目指す場所)ということで長期的で、『目標』は目的に達するまでの指標なので短期的なものになります。
そして、『目的』は痩せたい、幸せになりたい、家族で笑顔に過ごしたいなど抽象的となるとこに対して、目標は「より具体的な方がいい」と聞いたことがある方も多いと思いますが、まさにその通りです。
欲を言えばどれだけ目標を具体的にできるかが重要になります。
例)ダイエットの例
「目的」=「痩せる」
「目標」=「食べる量を減らして1ヶ月後には5kg痩せる」「週に5回、1時間以上は歩く」
上の例で目的である「痩せる」だけを決めていても、何をすればいいかわからなくなります。
そして、目的が達成できないまま終わってしまいます。
リハビリ現場で考えてみましょう。
目的を見失うと本当に望む結果が得られなくなる可能性があります。
目標が目的となっているリハビリ例)
目的=「手足を良くするためのリハビリをする」
目標=「ストレッチやマッサージをする」「歩行練習をする」
目標が目的になってしまうと、本来の目的を見失ってしまいます。
目的を見失うと望む結果を得られなくなります。
「手足を良くするリハビリをする」が目的になると、「手足が良くなっていても、違うリハビリでもっと良くなるかもしれない」とリハビリ依存になってしまいますね。
そうなると、時間だけ過ぎて満足いかないまま心も体もボロボロになる可能性ありますね。
『目的』を達成するための『目標』は具体的で細かく設定した方がいい
上でカーナビやダイエットで例をあげて説明していますが、この『目標』はより具体的で細かく設定した方がいいです。
なぜなら、達成感をその都度感じれる、何かあったら軌道修正ができるからです。
『目的』に対して『目標』が1〜2個しかないと、目標を達成するまでに時間がかかってモチベーションが続かなくなります。
しかし、『目標』を10個以上細かく設定しておくと、どんなに小さな目標でもクリアできたら嬉しいですよね。(マリオゲームで1-1をクリアして嬉しく感じる)
つまり、モチベーションが上がります。
また、『目標』を立ててもうまくいかないこともあります。そんな時、目標が細かく設定してあると、「じゃあ別の手段で目標を立てよう」など大きな目的や目標の中間地点は変わらないが軌道修正ができますね。
なので、『目標』は具体的で細かく設定することが大切なんです。
具体的で細かい目標設定
・小さな目標でも達成できるとモチベーションアップ
・失敗した時に軌道修正ができる
『目標』を具体的にするには知識が必要
『目標』を具体的にすることで目的が達成できることがわかったと思います。
しかし、目標立てるって難しいですよね。
なぜ難しいかというと、自分自身を知らないことと、知識が無いからです。
自分自身を知らないとなぜ目標が立てれないのかについては、人間は自分の好きなことや興味があることで無いと長続きしません。
長続きしないことを目標にしても意味がないですね。
↓↓継続するためのコツの詳細はこちら↓↓
もう一つの知識が無いからについては、例えば「ダイエットして痩せたい」という目的があっても、ダイエットの方法を知らなければ何をしていいか分かりませんよね。
リハビリも同じで、「手を楽に動かしたい」「楽に長い距離歩けるようになりたい」と目的があっても、効果的なリハビリ方法を知らないと何をしていいか分かりませんね。
ここでいう知識というのは、医療従事者はもちろん持っておかないといけないことなんですが、当事者や家族の方も知識として知っておかないといけません。
なぜなら、体を動かすのは当事者本人であり、医療従事者では無
『目標』を立てることでのメリット
上記のように、『目標』がどんどん達成できることによって、その方の『目的』に少しずつ近づきます。
また、『目標』が達成でいなくても、改善して新たな『目標』をその都度立てることで、最終的な『目的』の実現のために良い方向へと導いてくれます。
このように『目的』を達成するための『目標』を決め、実行して、結果を確認し、新たな目標を立てるといった良いサイクルが作れるようになります。
このサイクルが作れたら、もう迷うことはありませんね。
まとめ
リハビリ現場でも『目的』と『目標』を同じように使っている方は多くいます。
そして、当事者の方も同じように捉えていることから「手がもっと楽に動けるようになりたい」や「楽に歩けるようになりたい」が『目標』になっている場合が多くあります。
まずは言葉の意味から把握することもとても重要で、理解することで今の自分自身を振り返ることができます。
そこからがスタートではないでしょうか。
目標とは、人が一歩でも成長するために必要な指標になります。
高すぎても、簡単すぎてもダメで、達成できる目標にすることが重要です。
そのためには自分自身を知ること、知識を知ることが重要だと私は考えています。
“脳カラ”では、リハビリの目標設定についても「ひとりでできる」方法を一緒に学ぶ機会も作っております。
詳細は公式LINEから情報発信していますので、是非公式LINEに登録してください。
脳カラ公式LINEへの登録お願いいたします。
公式LINEに登録するとリハビリに関する限定情報を受け取ることができます。
また、個別相談もしているので、是非ご登録ください。
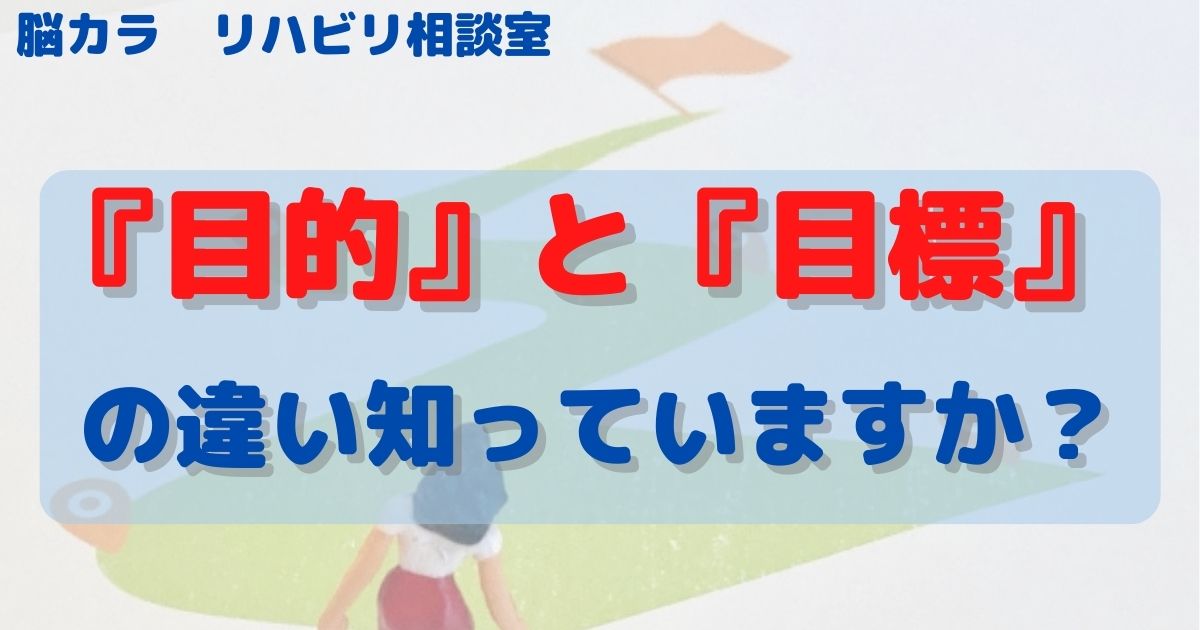



コメント