
Aさん
リハビリしないと動けなくなる・・・
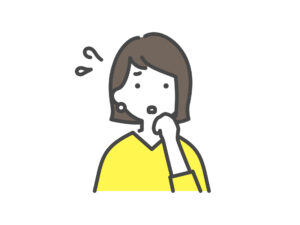
Bさん
今日もリハビリができなかった・・・
リハビリの成果がでないのは自分がダメだからだ・・・
リハビリにおいて運動も重要ですが、心の健康はもっと重要になります。
しかし、多くの片麻痺当事者の方でこの様な不安を抱えている方も多いと思います。
この漠然とした不安はリハビリ場面においてその方の成長や変化を阻害する場合が多くあります。
今回は、片麻痺当事者のリハビリ場面においての漠然とした不安の正体と最後に付き合い方についてまとめていきます。
不安とは?
不安とは誰もが普通に経験する神経質、心肺、困惑の感情です。
MSDマニュアル 家庭版より印象
不安とは、心配に思ったり、恐怖を感じたりすること。または恐怖とも期待ともつかない、何か漠然として気味の悪い心的状態や、よくないことが起こるのではないかをいう感覚(予期不安)である。
Wikipediaより引用
上記で言われている様に、不安は全ての人がたびたび体験する普通の感覚のことです。
つまり、不安を感じることはなんの異常はないことです。むしろ不安があるから行動に移したりと自身の「アラーム」の役割として大きな役割を果たしていると言われています。
- 心配している
- イライラしている
- 緊張している
- くよくよしている
- 気が休まらない
- 気が動転している
- 何かが気がかり
- 自信がない
- 落ち着かない
- 焦りを感じる
- ためらう様になる
不安は心だけの問題ではない
不安とは「憂鬱」などイメージがあると思いますが、心だけでなく身体にも影響を与えます。
例えば、不安が募ると頭痛・発汗・動悸・腹痛・下痢などさまざまな身体症状が起こることがあります。
- 下痢をする
- 筋肉が緊張している
- 動悸がする
- 脈が速い
- 足にピリピリ感がある
- 震えが止まらない
不安がパフォーマンスに与える影響
不安は最初のうちは不安に比例してパフォーマンス(特定の行為)が向上するなど良い影響を与えますが、一定以上すぎるとパフォーマンスが低下するといった悪影響を与えると言われています。
そして、不安どんどん高まった時に「痛み」「苦痛」といった身体症状となり対処不能な状態になります。
不安と恐怖を明確にする
ネガティブな心情について「不安」と「恐怖」という言葉があります。
この二つの違いは、対象が明確か不明確かの違いです。

C氏
リハビリをしないとなんか不安だ・・・
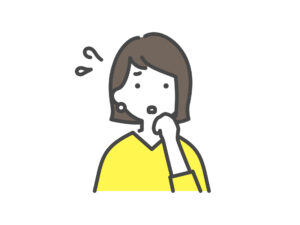
D氏
リハビリしないと足腰の筋力が落ちて転倒することが恐怖だ・・・
この様に、「なんだかわからないけど不安」「転倒することが恐怖」といった対象が明確なのか不明確なのかが違いになります。
恐怖は避ければ回避できますが、不安は回避することができません。
不安との付き合い方
不安が悪いところは、「何か知らない漠然としたことを常に頭の中に浮かべ」「回避できない」ため心理的負担がどんどん蓄積されることです。
不安を明確にしていくことで回避できることにしていくことがとても大切になります。
不安を明確にするための方法は、自分自身と対話することや人に話を聞いてもらうなどコミュニケーションがとても重要になります。
こちらの記事に詳細を書いていますので、興味ある方はご覧ください。
そして、不安と共存したり不安と適切な距離をとりながら過ごすことが大切です。
まとめ
この記事を書く上で参考にた記事サイトの公認心理士の方が書いていた言葉をご紹介します。
不安の嵐がやってきても、しばらくは身を任せてください。
パニック発作で死ぬ人はいません。台風が通り過ぎると、また普段のあなたがそこにいます。
不安を楽しむまではできませんが、この感覚を味わうことが、自分に対する「今自分が抱えている課題」を示してくれています。
不安と聞くとネガティブな印象を持つ方がおおいですが、実は今の自分が抱えている課題として捉えると乗り越えられることって思える様になりますね。
読んでくださった方で、「リハビリしないと不安という思いをずっと持っている」という方はぜひ石飛にご相談ください。
電話相談も無料で行なっています。
また、LINEでの個別メッセージにも対応していますので、是非あなたが感じている漠然とした不安を解決したい方は友達追加していただきご連絡ください。





コメント
何が良かったのか?悪かったのか?を今まで自分であまりに考えてこなかった、つくづく考えます!医学的な事を医師や訓練士さんへ任せてました。この記事を読んで、当事者意識から考える事が大切だと思います。
不安や恐怖心がストレスに繋がるのは、よくあります。先日肩痛があり血圧も高いので心配しました。船場センターの船場寄席でシンデレラエキスプレスや落語を聞き、上の事が治りました。接骨院で筋肉痛ほぐしも必要無くなりました❣️そして訓練意欲や料理の意欲も湧いてきたのです。
どうしても療法士や医師の言っていることが間違いない、正しいと思うことはあります。もちろん間違ったことを言っているわけではないのですが、決めるのは本人であり、変化するのは本人なので「自分で決める」といったことは重要になりますね。
そして自分で考えた上で決めることで「自分で決めたから」と割り切れることもあるので不安などの気持ちも少なくなる可能性があります。
和田さんは血圧や痛みの減ってきているということでいい方向に進めていますね。
またいろいろチャレンジしていきましょうね。