みなさんはリハビリスタッフにどのようなイメージを持っていますか?
- 自分の体を良くしてくれる人(歩行や手の動き)
- 何も言わなくても適切なリハビリをしてくれる人たち
国家資格をもっていることや、医療従事者というだけで勝手にこのようなイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、このイメージがもたらす心理的な影響(不安やイライラといった)について説明していきます。
リハビリを受けられている方にとって、リハビリスタッフに持つ期待は、良い面にも悪い面にも影響する事なので是非ご覧になってください。
理学療法士とは?リハビリテーションとは?_
理学療法とは病気、ケガ、高齢、障害などによって運動機能が低下した状態にある人々に対し、運動機能の維持・改善を目的に運動、高熱、電気、水、光線などの物理的手段を用いて行われる治療法です。
日本理学療法士協会HPより
「理学療法士及び作業療法士法」第二条には「身体に障害のある物に対し、主としてその機能的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう」と定義される。
理学療法の直接的な目的は運動機能の回復にありますが、日常生活動作(ADL)の改善を図り、最終的にはQOL(生活の質)の向上を目指す手法を用いる職業が理学療法士です。
つまり、対象者の症状や状態、希望に合わせて根拠のある治療法を用いて運動機能を維持・向上して、ADL(日常生活動作)とQOL(生活の質)の向上を目指すということです。
定義だけ見ると「自分の体を良くしてくれる人」「何も言わなくても適切なリハビリをしてくれる人たち」と思うのは無理ないですね。
実際に世界保健機関(WHO)の定義にも以下のように示されています。
リハビリテーションとは能力低下の場合に機能的能力が可能な限り最高の水準に達するように個人を訓練あるいは再訓練するため、医学的・社会的・職業的手段を併せ、かつ調整して用いること
世界保健機関WHO 1968
期待しすぎるあまり任せっきりになることも
「リハビリを受ければ良くなる」「また前のように歩けるためのリハビリをしてくれる」と思っている方も多いんじゃないでしょうか?
期待しすぎると他人に任せっきりになってしまって、期待した結果がなければ落胆するし、結果が出てももっと変わるんじゃないのか?となどネガティブで受け身の思考になってしまいます。
しかし、リハビリテーションで関わる理学療法士などリハビリスタッフも万能ではありません。
もちろん一人一人に合ったリハビリ方法を指導してくれたり、自立に向けて一緒にサポートする仕事ではありますが、リハビリをするのあくまで自分自身ということを頭に入れておく必要がありますね
「〇〇してくれるんじゃないの?」という疑念から始まるリハビリ不信
ここからは実際に相談をいただいた方で、リハビリ不信になっている方とのやりとりをご紹介します。

ご相談ありがとうございます。
今日の相談内容を教えてください。
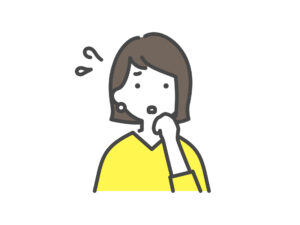
今、訪問リハビリを受けています。
私がこんなことがしたい、あんなことがしたいと伝えても、「そうなんですね」「できれば良いですね」と返事するだけなんです。

Aさんはやりたいことのご希望がたくさんあるのですね。
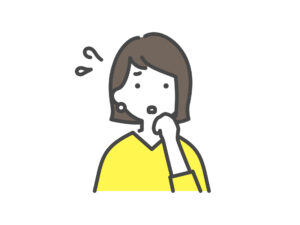
そうなんですよ。
それに向けて私はなにもわからないので、訪問リハビリの方には、段階を考えて細かい目標を立てて欲しいとお願いしています。

目標を立ててもらっているのですね。
その目標は細かく立ててもらっていますか?
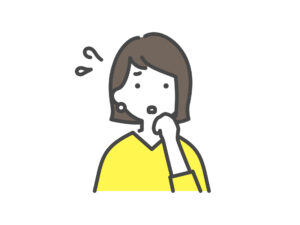
それが・・・「できれば良いですね」で終わっています。
実際に目標が分からず、リハビリもマッサージだけなんです。
これがもう3ヶ月も続いています。
もうどうすればいいのか分からなくて。

先が見えなくて不安なんですね。
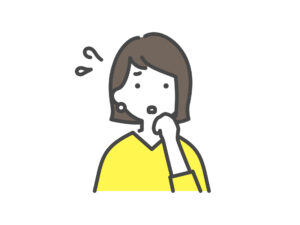
リハビリって専門家として、私の体に合わせて段階を考えてくれるんじゃないんですか?
これが、相談し始めの対話の一部始終です。
Aさんとして不安や課題を解決したいから訪問リハビリをサービスとして利用しているのに、納得のいく目標設定や実際のリハビリが受けれないことで不安が増大している様子でした。

あれができるようにやこれができるようにといったAさんの言葉をもっと深く知りたいです。
実際にリハビリの方には何ができるようになりたいと伝えられたのですか?
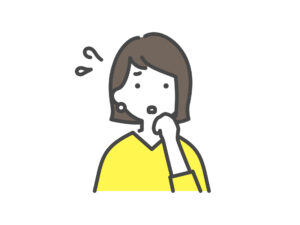
手の指がグーパーできるようになりたいと伝えています。

それだけですか?
手がグーパーできるようになることがAさんにとってなぜ大切だと思われているのですか?
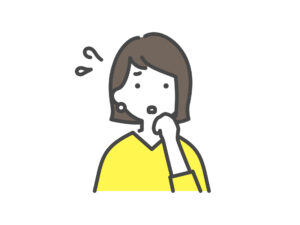
えっ・・・なぜ?
手がグーパーできればいろんなことができるようになるから…です

いろんなことをしたいと思われているのですね。
では、「いろんなこと」とはどのような動きだったり、動作のことなんでしょうか?
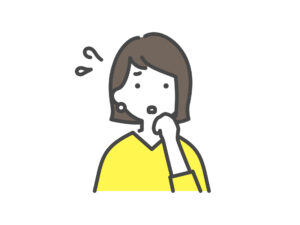
う〜ん
料理を作る時に麻痺手が使えると子どもたちに美味しい料理が作れる。
いつも負担をかけている家族を少しでも楽にしてあげたい。

家族様に負担をかけていることに対して不安や課題を感じていたのですね。
料理が少しでも手伝えたり、作れると家族様も楽になりますね。
そのことは訪問リハビリの方には伝えているのですか?
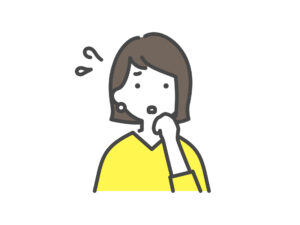
いいえ。
伝えていないです。聞いてくれないと思っていたので。
と、一連の対話の流れ(省略している部分もありますが)を記しました。
初めは手のグーパーができないことやそれに対してリハビリがマッサージだけとなっており、変化しないことに漠然とした不安を感じていたようです。
しかし、よくよく話を聞くことで、不安や課題のもとになっている根本は家族への負担をかけていることだったと本人も気がついた様です。
この後どのように訪問リハビリの方と具体的な目標を決めるかが重要になりますが、今までの『訪問リハビリの方が決めてくれる』というスタンスから、『一緒に決める』というスタンスで目標が具体的に決まるのでリハビリ方法ややり方も変わるんじゃないかと思っています。
まとめ
いかがでしたか。
今回は、リハビリスタッフへの「〇〇してくれるんじゃないの?」という期待を持っていた方がリハビリ不信になった一例をご紹介しました。
もちろんリハビリ職にこのように期待されることは当然だと思います。
しかし、自分自身がリハビリをすることによって“どう言う姿になり”、“どういったことをできるようになる”のかを共有できていないとリハビリ内容に納得することはできないと思います。
目標や目的を共有した上で、当事者の方も納得した形でリハビリを進められることが重要で、納得することで不安や不信はなくなると思っています。
不安や不信は言いづらいし、積もり積もって自分にのしかかるものです。少しでも軽くして目標に向かって前進できることが一番良いですね。
脳カラ公式LINEへの登録お願いいたします。
公式LINEに登録するとリハビリに関する限定情報を受け取ることができます。
また、個別の目標設定に関しての相談も受け付けていますので、是非ご登録ください。



コメント